本日の質問

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。
今日は「食物繊維の正体」ということについてお話していきたいと思います。
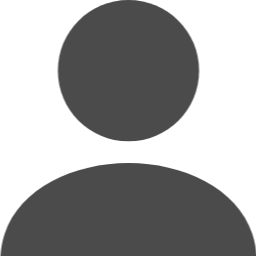
食物繊維のとりすぎは何か体に悪影響を及ぼすのですか?
海藻類、豆類、野菜が好きなので、おそらく1日に食物繊維を多く摂っていると思うのですが、具体的にどのような影響があるのか知りたいです。
今日はこの質問に回答していきます。
ではここから回答していきます。
結論
食物繊維は、不溶性:水溶性を2:1のバランスで摂取することが重要です。
食物繊維、それ自体は皆さんご存知だと思います。あのお通じ良くするやつですね。
食物繊維が足りてないと便秘になったり、下痢になったりします。
今回はこの知っているようで詳しくわからなない食物繊維についてお話していきたいと思います。
食物繊維は第六の栄養素?
以前、五大栄養素として炭水化物とタンパク質の話はしました(脂質はまだですが)。
今回はそれ+1、正確には六大栄養素という呼ばれ方はしてないですが、通称として5大栄養素+1とされている”食物繊維”についてです。
僕もトレーナー関係の仕事をして初めて知ったんですけど、食物繊維って実は2種類あります。
水に溶けやすいものと、溶けにくいもの。
それぞれ用途と役割が違うので解説していきたいと思います。
そもそも食物繊維とはなんぞや
その前に食物繊維はそもそも何かというと、人間にとって消化できないものです。
人間は食事を通して栄養素を吸収し、不要なものは便や尿として排出します。
ということは、人間にとって必要な栄養素は基本的に消化吸収されるということです。
つまり消化吸収できない物質が人間にとって不要な物質で、それが排出されるということです。
具体例としては肉は基本的に全て消化吸収されます。
しかし白米は炭水化物なので、分解された残り滓が生じます。
これが食物繊維です。
つまり食物繊維とは人間には分解できない物質ということです。
ただ、ここで気をつけなくてはならないのは、「人間が消化できないもの=どの動物にとっても消化できないというわけではない」ということです。
ヤギでいうと
例えばヤギ。
小学生とかで動物園とかいくと
「ヤギに紙食べさせていけません。」
と言われますよね。
人間は紙を消化できないので、食べると紙がそのまま便として出てきます。
しかしヤギとかの草食動物は、草を分解してエネルギーにします。
我々でいうとデンプン。
例えばお米はデンプンでできており、そのデンプンを分解すると糖の最小単位のグルコースになります。
なのでグルコースを大量にくっつけるとデンプンとなるわけです。
これと同様に、我々にとってのデンプン(米)は草食動物にとってのセルロース(紙)だということです。
ではなぜヤギに紙が分解できるのに人間に紙は分解できないのでしょうか?
ここで酵素について少し触れます。
全ては酵素の有無次第
ポイント:消化できるかどうかは、特定の「酵素」を持っているかどうかで決まります。
酵素という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
よく「酵素の力」や「酵素ドリンク」というフレーズで聞くものです。
そもそも酵素は何かというと、触媒の一種です。
触媒とは何かというと、化学反応をスムーズに進めるためのキーアイテムです。
基本的に化学反応を起こすには多くのエネルギーが必要になります。
この場合のエネルギーとは、ズバリ熱です。
なので化学での実験では、フラスコを熱するわけですね。

フラスコを熱することにより、エネルギーを与える
例えば本来80度の熱が無いと行われない化学反応を、もっと効率よく行うために触媒を導入します。
これにより40度の熱で同じ反応が進むことがあります。
これが触媒効果です。
そしてこの触媒は何でもよいのかというと、そうではありません。
Aという反応には触媒A、Bという反応には触媒Bというように各反応ごとに決まっています。
そして酵素とは体内で作用する触媒のことです。
つまり酵素はすごい働きをする、何でも働く魔法の物質みたいに言われてますけどそんなことはない、一定条件下で一定の反応を手助けするだけです。
ここ最近では酵素で痩せるとか酵素を取るだけで代謝が良くなるとか言いますが、この説明を聞くとありえないということがわかると思います。ある特定条件下でしか反応しないので 。
セルロース(紙)を分解する酵素を人間は持っていない
酵素の働きは何も合成だけではなく、分解する働きももちます。
例えばデンプンを分解する酵素アミラーゼ。
小学生の時にヨウ素液を使って実験したように唾液にはアミラーゼという消化酵素が含まれており、デンプンという塊があった時にそれを包丁のように切って、細かくします。
このアミラーゼを人間は持っているため、デンプンを分解でき、米を消化することができます。
一方セルロースを分解する酵素もあり、 それを我々人間は持っていません。
その酵素を持っていないので、口にすると体内のどこでもセルロースから分解されずにそのまま出てくるということです。
この消化できずに出てくる物質が食物繊維ということです。
2種類の食物繊維
食物繊維には大きく分けて「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の2種類があります。
不溶性食物繊維
冒頭で食物繊維は2種類あると言いました。
水に溶けやすい方と溶けにくい方です。
まず水に溶けにくい方、これが不溶性食物繊維(元の文では難溶性でしたが、一般的な不溶性を使用)。
これが大体の方が想像する食物繊維です。
この食物繊維は水に溶けないので、水を含むとかさが増します。
豊富に含んでいる食品として
- きのこ類
- ほうれん草などの葉物野菜
- 大豆などの豆類
- 穀類(玄米、全粒粉パンなど)
- いも類
です。
注意点: カサが増すので摂り過ぎてしまうと逆に便秘になることがあります。
水溶性食物繊維
一方、水に溶けやすいもの、こちらを水溶性食物繊維といいます。
この食物繊維は水に溶けるとスライムみたいなゲル状になります。
何に含まれているかというと、
- わかめ・もずくなどの海藻類
- こんにゃく(グルコマンナン)
- 果物(ペクチン:りんご、みかんなど)
- 大麦などの穀類
- ごぼうなどの根菜類
です。
こちらは水に溶けペースト状になるとドロドロになるので、摂りすぎると下痢になることがあります。
摂取におすすめの比率は‥
重要:不溶性食物繊維と水溶性食物繊維はバランス良く摂ることが大切です。
理想的な比率は、不溶性食物繊維:水溶性食物繊維 = 2:1 と言われています。
水溶性食物繊維を1摂ったら、
その2倍の量の不溶性食物繊維を摂ることが大切ですよというお話です。
まとめ
- 食物繊維は、人間が持つ消化酵素では分解できない物質です。
- 食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があります。
- 不溶性食物繊維:カサを増やし便通を促しますが、摂りすぎると便秘の原因にも。 (例: きのこ、葉物野菜、豆類)
- 水溶性食物繊維:ゲル状になり便を柔らかくしますが、摂りすぎると下痢の原因にも。 (例: 海藻類、こんにゃく、果物)
- 理想の摂取バランスは 不溶性:水溶性 = 2:1 です。
バランスの取れた食物繊維の摂取を心がけましょう!



コメント